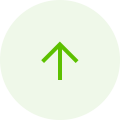こんなお悩みはありませんか?
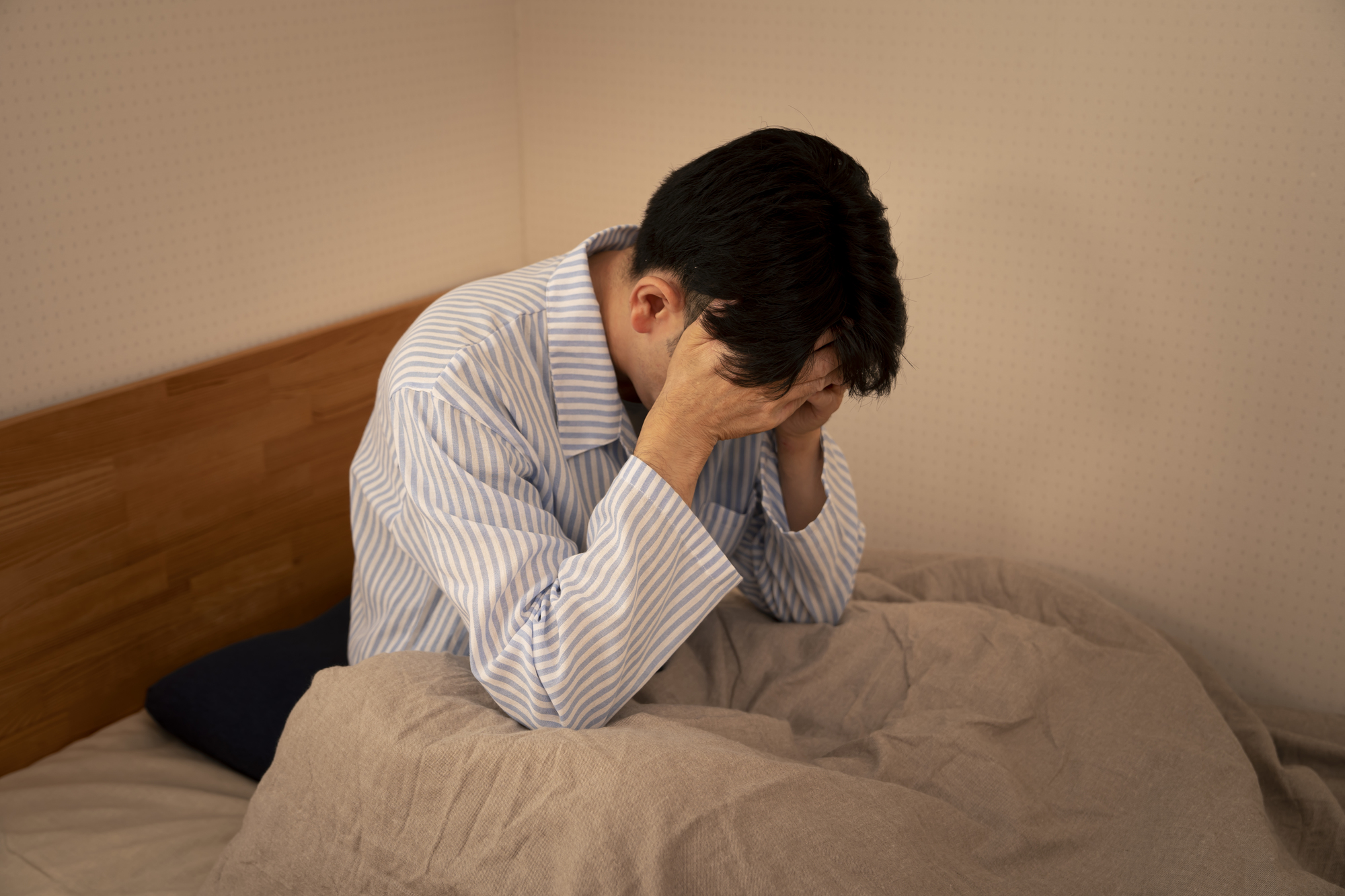
- 布団に入ってもなかなか眠りにつけない
- 寝てもすぐに目が覚めてしまい、熟睡できた感じがしない
- 夜中に何度も目が覚めてしまい、その後なかなか寝つけない
- 朝、起きたい時間よりも2時間以上早く目が覚めてしまう
- 睡眠時間は足りているはずなのに、寝た気がせず疲れがとれない
- 日中にだるさや集中力の低下、気分の落ち込みやめまいを感じる
- 「また眠れないのでは」と不安になり、ますます眠れなくなってしまう
など
このような症状がある場合は、
「睡眠外来」の受診をおすすめします。
睡眠外来(不眠外来)について
「なかなか寝つけない」「途中で何度も目が覚める」「早朝に起きてしまう」など、睡眠の悩みを抱えている方は多くいらっしゃいます。規則正しい生活や運動、スマートフォンの使用制限など、睡眠に良いとされる生活習慣をどれだけ心がけても、年齢やストレス、環境の影響によって、眠れなくなることは誰にでも起こりうることです。
慢性的な寝不足は、うつ症状や集中力の低下、肌荒れ、体調不良、さらには生活習慣病のリスクを高めるなど、心身に大きな負担を与えます。そのようなときは、一度当院までご相談ください。必要に応じて適切な睡眠薬を使うことも大切な選択肢です。現在の睡眠薬は、依存性や副作用が少ないものも多く、症状やライフスタイルに合わせて安全に使えるようになっています。
不眠症のタイプ
入眠障害
入眠障害とは、よくみられる不眠症で、布団に入ってから眠れるまで30分~1時間以上かかり、日常生活に支障をきたしている状態のことを言います。原因は緊張やストレスによるものが多いと言われています。
中途覚醒
中途覚醒とは、睡眠中何度も目が覚めてしまい、一度目覚めると再び寝つくまで時間がかかる状態のことを言います。高齢になるほど増加するのが特徴です。加齢により睡眠が浅くなることが原因の一つだと言われています。また、その他の原因としてはストレスや睡眠覚醒リズムの不調、うつ病、シフトワークなども挙げられます。
早朝覚醒
早朝覚醒とは、目覚まし時計で起きる予定の時刻よりも2時間以上早く目が覚めてしまい、その後再び眠れなくなる状態を指します。原因の一つに加齢があります。年齢を重ねると、体内時計のリズムが前倒しになり、自然に早寝早起きとなる傾向があります。また、うつ病も早朝覚醒を引き起こす原因になることがあります。
熟眠障害
熟眠障害とは、十分な睡眠時間を取っているのに、ぐっすり眠った感覚(熟眠感)が得られない状態のことを言います。睡眠時無呼吸症候群や周期性四肢運動障害などが原因のケースもあるため、検査する必要があります。
睡眠外来(不眠外来)の治療は
どんなことをするのか?
不眠症の治療は、睡眠に影響を与えている原因やタイプに応じて内容が変わりますが、主な対処法としては、「生活習慣の改善」と必要に応じた「薬物療法」が挙げられます。
生活習慣の改善

- アルコール、ニコチン、カフェインなどの刺激物は眠りを妨げるため、できるだけ控えましょう。
- 日中、外に出て太陽の光を浴びることで、体内時計をリセットし、夜の自然な眠気を促します。夜は照明を暗くしておくことも大切です。
- 午後にストレッチや軽い有酸素運動を定期的にすることで、心地よい疲労感から眠りやすくなります。
- 室温はやや涼しめ(約20度)に保ち、寝具の硬さや枕などは自分に合ったものを選びましょう。
- 音楽、読書、入浴など、ご自身に合った寝る前のリラックスできる習慣を見つけましょう。
- 眠たくなってからベッドに入りましょう。就寝時刻にこだわりすぎる必要はありません。
- 眠れない時は一旦、寝室から離れてみることも大切です。また、無理に眠ろうとしすぎないこともポイントです。
- 前日あまり寝むれなくても、起きる時刻は一定にしましょう。
薬物療法
服用中のお薬を確認
高血圧の薬(降圧薬)、甲状腺ホルモン剤、ステロイド、抗うつ薬などの一部には、不眠を引き起こす副作用があるため、必要に応じて現在服用しているお薬を調整していきます。
内科的アプローチ
バセドウ病などの甲状腺疾患、クッシング症候群や褐色細胞腫などの内分泌疾患、また不整脈や更年期障害などが原因で不眠の症状が出ることがあります。血液検査や心電図検査などの検査をし、内科的に原因がないかを調べることも重要です。
症状に応じて睡眠薬や漢方薬を処方
睡眠薬にはいくつかの種類があり、作用の仕方や効果の持続時間が異なります。当院では、お一人おひとりの状態や生活スタイルに合わせて適切なタイプ・用量を選び、丁寧にご説明した上で処方いたします。依存や副作用が心配な方もご安心ください。現在では安全性の高い薬も多く登場しており、必要に応じて段階的に使用・調整していくことで、無理なく不眠を改善することが可能です。
主に使用されるお薬の種類
- ベンゾジアゼピン系睡眠薬(ハルシオン、デパスなど):即効性があり、入眠を助けますが慎重に使用します。
- 非ベンゾジアゼピン系睡眠薬(マイスリー、ルネスタなど):比較的新しいタイプで、副作用が少なめです。
- メラトニン受容体作動薬(ロゼレムなど):体内時計を整える作用があり、自然に眠れるよう促します。
- オレキシン受容体拮抗薬(デエビゴ、ベルソムラなど):脳の覚醒を抑え、自然に近い眠りを誘います。
-
漢方薬(加味帰脾湯、柴胡加竜骨牡蛎湯など):患者様の状態に合わせて使い分けをしていきます。自立神経などを整える効果が期待できます。
- その他(抗不安薬・抗精神病薬・抗うつ薬など):症状や背景に応じて使用します。精神疾患の要素が強く、抗精神薬や抗うつ薬などの治療が必要な場合は、連携している精神科を紹介させていただきます。