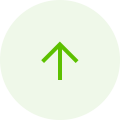気管支喘息・咳喘息

喘息は、気管(空気の通り道)が長い間炎症を起こしている状態で、ホコリやたばこの煙、ストレス、ペットの毛などの刺激に敏感に反応してしまいます。そのため、突然気管が狭くなり息苦しくなる発作を繰り返す病気です。
お子様の喘息の多くは「アトピー型喘息」と呼ばれ、特定のアレルギーが原因ですが、大人の喘息はアレルギーの原因がはっきりしない「非アトピー型喘息」が多いです。夜から明け方に症状が悪くなりやすく、薬(鎮痛剤)で発作が出る「アスピリン喘息」や、運動後に発作が起こる「運動誘発性喘息」もあります。発作が起きると、「ヒューヒュー」や「ゼーゼー」といった息をする音がしたり、息苦しくなったりします。
喘息は発作がなくても、気管に炎症が続いているため、そのままにすると気管の壁が厚くなって固くなり、治りにくくなってしまいます。喘息が疑われる場合は、血液検査や胸のレントゲン、呼吸の検査、吐いた息に含まれる成分を調べる検査などを行い、総合的に診断します。
気管支拡張症
気管支拡張症は、何らかの理由で気管(空気の通り道)の壁が広がり、その状態が元に戻らなくなってしまう病気です。
気管支が生まれつき広がっている場合(先天性)と、肺結核や細菌による肺炎、長く続く呼吸器の感染症、また関節リウマチやシェーグレン症候群などの病気、カビ(真菌)に対するアレルギー反応が原因で起こる場合(後天性)があります。
気管支が広がると、緑膿菌などの細菌に感染しやすくなり、咳や痰(時には血の混じった痰)、熱、身体のだるさ、息苦しさ、体重が減るといった症状が出ることがあります。
睡眠時無呼吸症候群
 睡眠時無呼吸症候群は、眠っている間に何度も呼吸が止まる状態を繰り返す病気です。
睡眠時無呼吸症候群は、眠っている間に何度も呼吸が止まる状態を繰り返す病気です。
主な原因は肥満や、喉の奥にある扁桃やアデノイドの大きさが原因となることが多いです。代表的な症状は大きないびきで、睡眠中に十分な酸素が身体に行き渡らなくなります。そのため、心臓の病気(心不全、不整脈、狭心症、心筋梗塞)や脳卒中など、重い病気のリスクが高くなります。
また、日中に強い眠気を感じるため、運転中や仕事中に重大な事故を起こす危険もあります。睡眠時無呼吸症候群の患者様は、日本では約300〜400万人いると考えられています。しかし、実際に治療を受けている方はそのうちの1~2割程度にとどまっています。早めの検査と治療が大切です。
肺炎
肺炎は、細菌やウイルス、カビなどが原因で肺に炎症が生じる病気で、主な症状としては咳、痰、喘鳴(ゼーゼー・ヒューヒューというような呼吸音)、息切れ、高熱などが挙げられます。体力や免疫力が下がると発症リスクが高まりやすく、放っておくと重症化する可能性があるため、注意が必要です。
肺結核
肺結核は、結核菌が肺や気管支に感染することで発症する病気です。
結核菌が肺胞に到達して増殖した場合、約1~2割の方が肺結核を発症すると報告されています。糖尿病やがんを患っている方、低栄養状態の方、免疫抑制剤や副腎皮質ステロイド、生物学的製剤を使用中の方、胃の切除後の方、HIVに感染している方など、免疫力が低下した状態にあると発症しやすいと言われています。
2週間以上継続する慢性的な咳、体重減少、倦怠感などが主な症状ですが、こういった症状があまりみられず、発見や治療が遅くなるケースもしばしばあります。
非結核性抗酸菌症
(肺MAC症)
非結核性抗酸菌症とは、結核菌とは異なる種類の抗酸菌が原因で起こる病気です。特に多いのはMAC菌が原因の肺MAC症です。これは全体の9割を占めるとされています。
結核菌とは違い、非結核性抗酸菌は人から人へ感染することはありません。MAC菌を含めたこれらの菌は自然界の水回りや土壌、ホコリ、水道や貯水槽など様々な場所に広く存在しているため、私たちは誰もが日常生活で吸引している可能性があります。
感染後は数年から場合によっては10年以上をかけてゆっくりと進行するのが特徴で、ほとんどの場合予後は良好ですが、慢性の咳や血痰、呼吸不全などが生じるケースもあります。
間質性肺炎

間質性肺炎は、肺の炎症などによって肺の細胞の壁が硬くなり、空気を十分に吸い込めなくなるため、呼吸がしにくくなる病気です。加えて、酸素を取り入れて二酸化炭素を排出する働き(ガス交換)が上手くできなくなり、息切れや咳などの症状が現れます。
間質性肺炎の原因には、関節リウマチや皮膚筋炎といった病気(膠原病)、病院で使う薬や漢方薬、サプリメント、職場や生活環境で吸い込むホコリや石綿(アスベスト)、ペットの毛やカビなどがあります。
また、特殊な感染症が原因となることもあります。しかし、半数以上のケースは原因がはっきりしない「特発性間質性肺炎」と呼ばれています。特に「特発性肺線維症」は、喫煙歴のある50歳以上の男性に多くみられ、難病にも指定されています。
慢性閉塞性肺疾患(COPD)
慢性閉塞性肺疾患(COPD)は、長期間にわたりタバコの煙といった身体に有害な物質を吸い込むことで肺に炎症が起き、肺気腫や慢性気管支炎などが伴う病気の総称です。
喫煙開始時の年齢や喫煙本数、喫煙年数といったものに伴って発症リスクが高くなり、慢性閉塞性肺疾患(COPD)患者様のうち、およそ90%が喫煙者であると言われています。
主な症状は咳、痰、労作時呼吸困難(身体を動かしたときの息切れ)などで、階段の上り下りや少し早足で歩いた程度の軽い運動で息が切れる場合には注意が必要です。
肺がん
肺がんは、肺や気管支の細胞から発生する「原発性肺がん」と、他の臓器のがんが肺に転移した「転移性肺がん」に分類されます。悪性腫瘍は正常な組織に浸潤・破壊しながら増殖し、他の臓器へも転移するのが特徴です。
肺がんには肺腺がん、扁平上皮がん、小細胞肺がんなど複数の種類があり、進行度(ステージ)によって治療法や予後が大きく異なります。
初期には特徴的な症状がなく、咳、血痰、息苦しさ、発熱などが現れても、風邪などと区別がつきにくいため、進行するまで気づかれにくいことがあります。特に喫煙歴のある方や症状が続く場合は、早期発見のためにも胸部レントゲン(X線)検査などの画像検査を受けることが重要です。