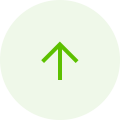痰がたくさん出る原因

痰がたくさん出るのは、身体が細菌やウイルスなどの異物を排除しようとしている防御反応です。通常、私たちの身体では1日に50〜100mLほどの痰が作られていますが、その多くは唾液と一緒に飲み込まれたり、自然に吸収されたりするため、気づかないことがほとんどです。
しかし、感染症や炎症が起こると痰の量が大きく増え、肺炎などの場合1日に1,000mL以上の痰が出ることもあります。また、細菌やウイルスだけでなく、タバコの煙やホコリなどの刺激物によっても痰が増えることがあります。痰が増えたからといってすぐに問題とは限りませんが、量が多く長く続く場合は、早めにご相談ください。
痰を出した方が早く治る?
痰は、ウイルスや細菌などの異物を外に出すために、身体がつくり出すものです。痰を出すことで、喉や気道の中にある炎症のもとになるウイルスや細菌も一緒に外に出されるため、呼吸が楽になったり、炎症を抑えることにつながります。そのため、無理のない範囲で痰は出すようにしましょう。
痰が絡むときの治し方
水分補給

少しずつこまめに水分(特に水や白湯)をとることで、痰が柔らかくなり出しやすくなります。空気が乾燥していると痰が喉に絡みやすくなるため、室内を加湿しておくことも大切です。
加湿
湯気(スチーム)を吸い込むと喉や気道が潤い、痰の自然な排出が促されます。入浴や蒸しタオル、吸入器の使用もおすすめです。
咳払い
激しく咳き込むのを避け、軽く「んっ」と咳払いを何回か行うことで、喉の痰が動きやすくなります。
体勢
上半身を少し前に傾けたり、うつむいたりすることで、痰が動きやすくなることがあります。
痰が絡むときの
受診の目安
次のような症状がある場合には、できるだけ早めに当院までご相談ください。
- 色の濃い痰が出る
- 呼吸が苦しい
- 胸に痛みがある
- 咳や痰が長期間続く
- 軽い運動(階段の上り下りなど)で動悸や息切れがする
- 咳が頻繁に出る
- 血の混じった痰が出る
など
痰が絡むときに
実施する検査
喀痰培養検査

喀痰(かくたん)培養検査は、痰の中にいる細菌やカビ(真菌)を調べる検査です。肺炎や気管支炎の原因となっている菌を特定することで、効果的な治療に役立てます。この検査には2つの方法があります。1つは、痰をガラスに塗って顕微鏡で見る方法(塗布検査)です。もう1つは、痰を専用の容器で育てて、どんな菌がいるかを詳しく調べる方法(培養検査)です。一般的な菌であれば、結果が出るまでに3〜5日ほどかかります。一方、結核菌のように育ちにくい菌は、結果が出るまでに6週間ほどかかることもあります。結核が疑われる場合には、朝一番の痰を3日間連続で採るなど、正確に調べるための追加検査を行うことがあります。
喀痰細胞診
喀痰(かくたん)細胞診は、痰の中に含まれる細胞を調べる検査です。痰には肺や気道の中から出てきた細胞が含まれており、これを顕微鏡で詳しく観察します。肺がんがある場合、がん細胞が痰の中に混じって出てくることがあります。そのため、この検査によって、がん細胞が見つかる可能性があり、肺がんの早期発見に役立つことがあります。咳や痰が続いている方、胸のレントゲン検査で異常が見つかった方に行われることが多い検査です。
痰が絡むときに
考えられる病気
肺炎
肺炎とは、肺にウイルスや細菌が感染し炎症が生じた状態です。代表的な症状には、咳、痰、発熱、息苦しさ、胸の痛みなどがあります。ただし、高齢の方ではこうした典型的な症状がはっきり現れないことがあり、受診が遅れてしまうことが多くあります。特にご高齢の方や持病をお持ちの方は、風邪だと自己判断せずに、お早めに当院までご相談ください。
誤嚥性肺炎
誤嚥とは、本来は食べ物や唾液が通るはずの食道ではなく、間違って気管に入ってしまうことを言います。この誤嚥は、飲み込みの働きが弱くなることで起こりやすくなります。誤嚥によって、唾液や食べ物、時には胃の中の液体と一緒に細菌が気管に入り、「誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)」という肺炎を引き起こすことがあります。誤嚥性肺炎の主な症状は、熱が出る・咳が出る・痰が出ることですが、これらのはっきりした症状がない場合もあり、なんとなく元気がない、食欲がない、喉がゴロゴロする感じがするといった軽い症状だけで気づきにくいこともあります。特に高齢の方や飲み込みが弱い方は注意が必要です。
気管支拡張症
気管支拡張症とは、先天的な要因や気管支に繰り返し起こる炎症などによって、気管支が広がってしまう病気を指します。主な症状としては咳、痰、血痰、喀血などが挙げられます。
気管支喘息
気管支喘息とは、空気の通り道(気道)に慢性的な炎症が起きることで様々な刺激に過敏に反応してしまい、発作的に気道が狭くなることを繰り返す病気です。代表的な症状は咳や痰、息苦しさ、呼吸困難の他、喘鳴と呼ばれる、「ゼーゼー」「ヒューヒュー」といった呼吸音が現れるのが特徴です。
咳喘息
気管支喘息と同様に空気の通り道(気道)が狭くなることによって引き起こされます。気管支喘息との違いとして、明らかな「ゼーゼー」「ヒューヒュー」といった呼吸音がないことが多いです。息苦しさや、喉から胸のあたりにかけての痒みなどの違和感が特徴です。
COPD(慢性閉塞性肺疾患)
慢性閉塞性肺疾患(COPD)とは、肺気腫や慢性気管支炎といった病気の総称です。長期間にわたる喫煙が主な原因で、発症すると咳や痰、息切れといった症状が現れます。また、喘鳴と呼ばれるゼーゼー・ヒューヒューといった呼吸音(喘鳴)や呼吸困難など、喘息と似た症状がみられることもあります。
肺結核
肺結核とは、肺に結核菌が感染することが原因で起こる病気です。主な症状は、咳や痰、血の混じった痰(血痰)の他、発熱、倦怠感、体重減少、寝汗なども現れます。また、肺結核は空気感染する感染症のため、感染者が結核菌を含んだ咳をすることで周囲の人に感染が拡大します。
肺がん
肺がんでは、咳、痰、胸の痛み、倦怠感、体重減少などの症状がみられることがあります。しかし、これらの症状は風邪や肺がんではない他の呼吸器疾患の症状にも似ているため、見過ごされることも珍しくありません。また、初期には自覚症状が現れないことも多いため、がんが進行してから発見されるケースもあり、注意が必要です。
後鼻漏
後鼻漏とは、鼻水が鼻の奥から喉の奥に流れ込む状態のことを言います。鼻水が喉に多く流れ込むことで、喉に違和感が生じたり、咳が出たりします。後鼻漏は、正確には喉に絡んでいるのは痰ではなく鼻水なのですが、患者様がご自身でこれらを判別することは難しく、多くの場合「痰が絡む」と感じます。
心不全
心不全になると痰が増えることがあります。心不全とは心臓の機能が低下した状態のことを言います。心臓の機能の低下により、肺に水分が溜まり(肺水腫)、そのことにより痰や咳が増えます。この時の痰を「泡沫痰」と言い、泡状であったりピンク色がかっていることが特徴です。急な体重の増加、下腿のむくみ、横になると息苦しくなるなどの症状がある方は心不全の可能性があるので、すぐに病院を受診して検査をして下さい。