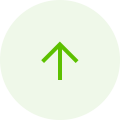当院では、ご家族で来院された際に、3歳前後のお子様も大人の方と同じ日に診察を受けていただけます。
こんな症状やお悩みはありませんか?

- 発熱(37.5℃以上)
- 咳
- 鼻水
- 喉の痛み
- 頭痛
- 腹痛、胃の痛み
- 下痢
- 倦怠感(身体のだるさ)
- インフルエンザが疑われる場合
(濃厚接触者も含む) - 新型コロナウイルス感染症が疑われる場合(濃厚接触者も含む)
など
このような症状がある場合は、「感染症内科」の受診をおすすめします。
※発熱外来について
当院では受診時に37.5℃以上の発熱がある方は、別室での対応となることがあります。
また、インフルエンザやコロナウイルスの流行時期には、感染対策のため抗原検査を勧めさせていただくことがあります。
御了承ください。
感染症内科について
 感染症は、細菌・ウイルス・カビ(真菌)・寄生虫などの微生物によって引き起こされる病気です。身近な例では、風邪・インフルエンザ・肺炎・胃腸炎なども感染症に含まれます。これらの微生物は、生活環境の中はもちろん、私たちの身体の中にも存在しているごく身近な存在です。当院では、発熱や体調不良など、感染症が疑われる症状がある方を「予約なし」で診療しています。
感染症は、細菌・ウイルス・カビ(真菌)・寄生虫などの微生物によって引き起こされる病気です。身近な例では、風邪・インフルエンザ・肺炎・胃腸炎なども感染症に含まれます。これらの微生物は、生活環境の中はもちろん、私たちの身体の中にも存在しているごく身近な存在です。当院では、発熱や体調不良など、感染症が疑われる症状がある方を「予約なし」で診療しています。
風邪のように見えても、実は別の病気が隠れていることもあるため、必要に応じて丁寧に診察・検査を行い、原因を見極めた上で治療を行います。不安な症状がある場合は、お気軽にご相談ください。
来院される方へのお願い
ご来院の際は「マスクの着用」をお願いしております。受付では「体温測定」と「手指の消毒」にもご協力ください。
感染症内科の主な病気
風邪

風邪(かぜ)は、鼻や喉にウイルスなどの病原体が感染して起こる病気です。主な症状には、発熱・咳・くしゃみ・鼻水・鼻づまり・喉の痛み・声のかすれなどがあります。ほとんどの場合、原因はウイルス感染ですが、まれに細菌(マイコプラズマやクラミジアなど)によって起こることもあります。風邪のウイルスはとても種類が多く、数百種類以上あると言われています。そのため、大人でも年に2~3回、子どもではもっと頻繁に風邪を引くことがあります。
さらに、同じウイルスでも毎年新しいタイプが出てくるため、何度もかかってしまうのです。インフルエンザなど一部を除き、風邪のウイルスには特効薬がないため、治療は辛い症状をやわらげるための「対症療法」が中心になります。多くの場合、身体の自然な回復力によって1週間ほどで治ることがほとんどです。
新型コロナウイルス(COVID-19)
COVID-19は、SARS-CoV-2というコロナウイルスによって起こる感染症です。発熱や咳などの「風邪に似た症状」から、肺炎や持病の悪化といった重い症状まで幅があります。最近は秋~冬に患者さんが増えやすい傾向があります。
新型コロナウイルスの初期症状
いわゆる風邪では「微熱・くしゃみ・鼻水・喉の痛み」が中心ですが、COVID-19では加えた味覚障害や強い倦怠感、高熱や強烈な喉の痛みが挙げられます。
※症状だけで風邪やインフルエンザと見分けるのは困難です。必要に応じて検査が必要です。
新型コロナウイルスの潜伏機関
感染から症状が出るまでの潜伏期間はおおむね2~5日です(個人差あり)。症状が出る少し前から人にうつす力が強くなる点に注意が必要です。発症の前後数日が最も感染させやすいと考えられています。発症後は日数とともに感染性が下がりますが、年齢や基礎疾患、免疫状態によって差があります。家庭・職場・学校ではマスク、手指衛生、換気が有効です。
新型コロナウイルスの流行時期
秋から冬にかけての流行だけでなく、近年は春~夏にかけての一時的な感染の流行もあり、通年を通しての感染が確認されています。
重症化しやすい方の特徴
次の方は肺炎や入院のリスクが上がりやすいとされています。
- 高齢の方、妊娠中の方
- 心臓・肺・腎臓の病気、糖尿病、肥満などの基礎疾患がある方
- 免疫が抑えられている方、透析中の方、喫煙者
など
該当する方や家族に上記の方がいる人は早めの受診・検査・治療相談をおすすめします。
インフルエンザ
インフルエンザウイルスによって引き起こされる感染症を「インフルエンザ」と言います。インフルエンザにはA型、B型、C型、D型の4つのタイプが存在し、ヒトに感染、流行するのは主にA型とB型のウイルスです。
インフルエンザの初期症状
風邪の症状は、微熱やくしゃみ、鼻水、咳、喉の痛みなどがあるのに対して、インフルエンザの症状は、38℃以上の高熱、全身の倦怠感、関節痛、筋肉痛、吐き気や下痢、腹痛といった消化器症状などが挙げられます。
インフルエンザの潜伏期間
インフルエンザは、感染してから症状が出るまでの「潜伏期間」が短いのが特徴です。人によって違いはありますが、通常1~3日ほどで症状が出始めます。ウイルスは身体の中に入ってからすぐに増え始め、たった1日で急に熱が出たり、全身がだるくなったりすることがあります。潜伏期間中はまだ症状がないため、自分では気づかないまま他の人にうつしてしまうこともあります。特に家族や職場、学校などでは注意が必要です。
インフルエンザの流行時期
インフルエンザは、毎年12月から3月頃にかけて多くの人がかかる感染症です。ただし、年によっては冬が始まる前の秋頃から流行し始めることもあります。インフルエンザにかかっても重い症状にならないようにするには、ワクチンの予防接種が効果的です。ワクチンの効果は接種してから5か月ほど続くとされています。そのため、毎年10月中旬~11月下旬までに接種しておくと、特に感染者が増える1月~2月頃にしっかりと効果を発揮できます。
百日咳

百日咳菌とも呼ばれる、ボルデテラ・パーツシスという細菌によって引き起こされる感染症を「百日咳(ひゃくにちせき)」と言います。その名の通り、長期間咳が続くことが特徴で、3か月(約100日)咳が続くこともあります。初期症状は軽く、風邪やインフルエンザに似ていますが、放っておくと症状が悪化して、長引くことがあります。
百日咳の初期症状
百日咳は、風邪のような症状から始まります。咳や喉の痛み、鼻水などが1〜2週間ほど続くため風邪と間違われることが多く、百日咳と気づかれにくいのが特徴です。その後、咳が段々ひどくなり、1回に何度も続けて咳き込む「咳の発作」が起こるようになります。特に夜は咳が出やすく、眠れなくなることもあります。咳が激しいと、息を吸うときに「ヒューッ」という音(喘鳴)が出ることもあります。この咳はとても長く続くことがあり、症状が落ち着いても、数週間から数か月にわたって咳が残るケースもあります。
百日咳の潜伏期間
百日咳は、感染してから症状が出るまでの「潜伏期間」が長いのが特徴です。長いと3週間ほど菌が潜伏するケースもあります。潜伏期間中でも感染は広まるため、知らない間に感染が拡大してしまうことも多くあります。
百日咳は一度かかったらかからない?
百日咳は一度かかると、身体の中で「抗体」がつくられ、しばらくの間は再び感染しにくくなります。ただし、この抗体の効果はずっと続くわけではないため、時間が経つと再びかかってしまう可能性があります。ワクチンを打つことでも抗体をつくれますが、こちらも効果がずっと続くわけではありません。そのため、定期的なワクチン接種が大切です。
百日咳は大人もかかる?
百日咳はお子様がよくかかる病気というイメージがありますが、大人も感染することがあります。特に、免疫が落ちていると感染しやすくなり、重い症状が出ることもあります。また、大人が気づかないうちに赤ちゃんや小さなお子様にうつしてしまうこともあるため、注意が必要です。
大人の百日咳の症状
大人が百日咳にかかった場合、お子様にみられるような特徴的な咳の発作が出ないこともあります。そのため、単なる風邪と思ってしまい、見過ごされがちです。人によっては肋骨が折れるほど強い咳が続くこともありますが、反対に軽い咳だけで自然に治ってしまうケースもあり、症状の重さや咳が続く期間には個人差があります。ただし、どんなに軽い症状であっても、発症から約2週間は他の人にうつす可能性が高いため注意が必要です。2週間以上、熱はないのに咳が治まらない、咳がひどくて吐いてしまうなどの症状がある場合は、お早めに当院までご相談ください。
マイコプラズマ肺炎
マイコプラズマ肺炎は、「マイコプラズマ菌」という細菌によって起こる肺炎です。一般的な肺炎とは異なり、聴診器で胸の音を聞いても、痰が絡むような音が聞こえにくいという特徴があります。これは、マイコプラズマ肺炎では、通常の肺炎で炎症が起こる気管支や肺胞ではなく、それらの外側にある「間質(かんしつ)」という組織に炎症が起こるためです。しかし、症状が長引くと炎症が気管支や肺胞にも広がり、痰が絡む音が聞こえるようになることもあります。
マイコプラズマ肺炎の初期症状
マイコプラズマ肺炎の初期症状は風邪と似ていますが、次のような特徴があります。これらの症状は夜にひどくなりやすいというのも特徴です。
- 1週間以上続く乾いた咳
- 微熱もしくは高熱が続く
- 痰はほとんど出ない
マイコプラズマ肺炎の潜伏期間
マイコプラズマは、感染してから症状が出るまでの「潜伏期間」が2~3週間と比較的長いのが特徴です。そのため、症状が出ていなくても、菌が体内に残っている可能性があります。しばらくは登校や通勤の際にマスクを着用するなどし、周りへの感染を防ぐよう注意しましょう。また、咳が治るまでは激しい運動は控えるようにしてください。
マイコプラズマ肺炎は一度かかったらかからない?
マイコプラズマ肺炎は、感染しても十分な免疫が体内にできることがないため、何回でも感染することがあります。
マイコプラズマ肺炎は大人もかかる?
マイコプラズマ肺炎は、14歳以下のお子様が8割を占めますが、大人でもかかることがあります。
大人のマイコプラズマ肺炎の症状
マイコプラズマ肺炎は、大人がかかると症状が長引きやすいため注意が必要な病気です。発熱は「弛張熱(しちょうねつ)」と呼ばれ、1日のうちで熱が上がったり下がったりする特徴的なパターンを示すことがあります。また、初めは乾いた咳から始まり、炎症が進むことで痰が絡む湿った咳に変わることがあります。特にご高齢の方では、呼吸不全や胸水を引き起こし、入院が必要になるケースもあるため、できるだけ早くご相談ください。