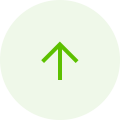酸素が足りない感じがするのはなぜ?

酸素が足りない感じがするというのは、医学的には「呼吸困難」や「息切れ」と表現され、原因には様々考えられます。
呼吸困難や息切れの原因
呼吸困難や息切れの主な原因には、呼吸器疾患、循環器疾患、脳の血管障害などがあります。その他に、貧血、更年期障害、甲状腺機能亢進症(バセドウ病)、過換気症候群もその一因となる場合があります。
慢性閉塞性肺疾患(COPD)
慢性閉塞性肺疾患(COPD)は、主にタバコの煙など身体に害のある物質を長期間吸い続けることが原因で肺に炎症が起こり、肺気腫や慢性気管支炎を伴う病気の総称です。慢性閉塞性肺疾患(COPD)では喫煙を開始した年齢や本数、喫煙を続けている年数などが発症リスクを高め、患者様全体のおよそ9割が喫煙者であると言われています。主な症状は咳、痰、身体を動かしたときの息切れ(労作時呼吸困難)で、激しい運動ではなくちょっとした運動(階段の上り下り、早足で歩くなど)程度で息切れがみられる場合、注意が必要です。
間質性肺炎
間質性肺炎は、肺に炎症が生じ、肺胞の壁が厚く硬くなる(線維化)ことによって空気を吸っても肺が十分に膨らまなくなってしまう病気です。また、厚くなった細胞壁によって正常なガス交換である酸素の取り込みや二酸化炭素の排出が妨げられるため、息切れや咳といった症状が現れます。原因としては関節リウマチや皮膚筋炎などの膠原病や、病院で処方される薬や漢方薬・サプリメントなどの健康食品、職業や生活上でのホコリや石綿、ペットの毛やカビなどの慢性的な吸入があげられる他、特殊な感染症が原因のケースもあります。しかし、症例の半数以上は特発性間質性肺炎という原因を特定できないものであり、中でも指定難病にも指定されている特発性肺線維症は喫煙習慣のある50歳以上の男性に多くみられると言われています。
気管支喘息
気管支喘息は、気道に起こる慢性的な炎症により、ホコリ、タバコの煙、ストレス、ペットの毛など、様々なものが刺激となり発作的に気道が狭くなることを繰り返します。小児喘息の多くは「アトピー型喘息」と呼ばれる、特定の物質へのアレルギー反応として生じるタイプですが、成人の喘息では「非アトピー型喘息」と呼ばれるアレルゲンが特定できないタイプがほとんどです。夜から明け方にかけて症状が悪くなりやすいのが特徴で、鎮痛剤の使用時の発作(アスピリン喘息)や運動の後の発作(運動誘発性喘息)が現れるケースもあります。発作時には、ヒューヒュー・ゼーゼーといった喘鳴(ぜんめい)が聞こえ、息苦しさを伴うのが特徴です。
心不全
心不全は病名ではなく、心筋梗塞や弁膜症などの心臓の病気で引き起こされる症状の総称です。心不全になると、心臓の機能が低下して全身に十分な血液を送り出せなくなります。結果として、様々な部位でうっ血や酸素不足が生じ、息切れや動悸などの症状を引き起こします。また、うっ血が肝臓や胃腸に及ぶと、吐き気・嘔吐・食欲不振といった消化器症状が出ることもあります。これらの症状がある方は、消化器だけでなく心臓の検査も検討することをおすすめします。
狭心症・心筋梗塞
狭心症は、心臓の血管(冠動脈)が狭くなり、一時的に血液の流れが悪くなることで胸の痛みや圧迫感が起こる病気です。身体を動かしたときやストレスを感じたときなどに症状が出やすく、しばらく休むと治まるのが特徴です。
心筋梗塞は、冠動脈が完全に詰まり、心筋への血流が止まることで心臓の組織が壊死してしまう重篤な病気です。突然の激しい胸の痛みや圧迫感、吐き気、冷や汗などが現れ、緊急の治療が必要です。これらの病気の主な症状は、胸の痛みですが、初期には運動時の息切れだけがみられることもあり、注意が必要です。
不整脈
不整脈は、心臓のリズムが乱れることで血液の循環がうまくいかず、息切れを引き起こすことがあります。脈が速くなる「頻脈」や、遅くなる「徐脈」、不規則に打つ「期外収縮」などのタイプがあり、それぞれで異なる症状が現れます。頻脈は、脈が1分間で120回以上になる状態で、心臓が効率よく血液を送り出せず、少し動いただけでも息切れや動悸が起こりやすくなります。徐脈は、脈が1分間で40回以下と極端に遅くなる状態で、脳や全身に十分な血液が届かず、息切れだけではなく、めまいやふらつき、意識が遠のくような感覚を伴うこともあります。これらの不整脈は、心臓の病気や自律神経の乱れが背景にあることも多く、放置すると命に関わるリスクもあるため、息切れが続く場合は早めに医療機関を受診しましょう。
息苦しいときは
どうすればいいか?
(対処法)
息切れがある状態で無理に運動を続けると、症状が悪化してしまう恐れがあります。まずは運動を中止し、楽な体勢をとって安静にするようにしましょう。それでも息切れが続く場合、当院までご相談ください。
受診の目安
- 胸の痛み、めまい、意識がもうろうとするなどの症状がある
- 突然、強い息切れに襲われた
- 安静にしていても息苦しさが続く
- 発熱や咳、痰が長引いている
息苦しいときに行う検査
息苦しさがある場合、まずは問診や血中の酸素飽和度の測定、胸の音の聴診、必要に応じて胸部レントゲン(X線)検査やエコー検査により肺や心臓の状態を診ます。さらに、血液検査を行うことで炎症の程度や貧血、心不全の有無を調べることも可能です。また、更年期障害や精神的な症状が原因である可能性が疑われる場合、専門の医療機関へご紹介します。少しでも気になる症状がある方は、我慢せずお早めに当院までご相談ください。