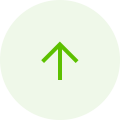咳が止まらないのは喘息?

通常、風邪などの感染症による咳は、長くても2~3週間ほどで自然に治まることが多く、それ以上咳が続く場合は、風邪だけでなく喘息やアレルギー、肺や心臓の病気など他の原因が関係している可能性があります。
咳が長引くときは、早めに呼吸器内科を受診して、適切な検査や治療を受けることをおすすめします。
気管支喘息と
咳喘息の違いは?
咳喘息は、咳が2~3週間以上、場合によっては数か月続く状態です。
気管支喘息のように、気道が狭くなって、ゼーゼー、ヒューヒューといった呼吸音(喘鳴)はみられず、咳だけが症状として現れます。そのため、風邪が長引いていると勘違いされやすいのが特徴です。この咳は感染症ではないため、うつる心配はありません。原因としては、気道に好酸球という白血球が集まり、慢性的な炎症を起こすことが挙げられます。炎症が起きている気道は、乾燥した空気、たばこの煙、冷気、花粉など、様々な刺激に過敏に反応しやすくなり、咳が出やすくなります。
咳喘息を放置すると、将来的に本格的な気管支喘息に進行してしまうこともあるため、注意が必要です。特にアレルギー体質のある方や、女性に多くみられ、再発を繰り返すこともあります。「熱はないし咳だけだから…」と放置せずに、当院までご相談ください。
気管支喘息について
気管支喘息は、空気の通り道である気道に慢性的な炎症が起こることで、少しの刺激でも気道が敏感に反応し、発作的に狭くなってしまう病気です。このため、「ヒューヒュー」「ゼーゼー」といった呼吸音や、咳・息苦しさといった症状が繰り返し現れます。日本では、子どもの約8〜14%、大人の約9〜10%が喘息を抱えていると言われています。
大人の気管支喘息の特徴
喘息は子どもに多い病気と思われがちですが、大人になってから初めて発症するケースも珍しくありません。特に、過労やストレスで体力が落ちているときに風邪をきっかけに発症することがあります。
また、喫煙や飲酒、ストレスといった生活習慣の影響を受けやすく、症状が長引いたり悪化したりしやすいのが特徴です。子どもの喘息と違い、大人の喘息はアレルギー反応がはっきりしない「非アトピー型」が多く、原因の特定が難しいこともあります。
気管支喘息の症状

気管支喘息では、突然咳が出たり、痰が絡んだりすることがあり、呼吸のたびに「ゼーゼー」「ヒューヒュー」といった音が聞こえるようになります。これらの症状に加え、胸が締めつけられるような息苦しさを感じることがあります。こうした状態を「喘息発作」と呼びます。
特に夜間や明け方に症状が強くなる傾向があるのが、喘息の特徴のひとつです。発作が軽い場合でも、繰り返すうちに気管支の壁が厚くなり、症状が悪化していく可能性があります。また一旦、気管支壁が厚くなると基本的に元に戻るのは困難とされています。
そのため、呼吸器内科医による専門的かつ早めの診断と治療が大切といわれています。
気管支喘息の原因
気管支喘息には、大きく分けて「アトピー型」と「非アトピー型」の2つのタイプがあります。それぞれ原因が異なります。
アトピー型喘息
「アトピー」というと皮膚の病気を思い浮かべるかもしれませんが、アトピー型喘息は気道でアレルギー反応が起こる病気です。アレルギーが原因で起こる喘息で、次のようなものが刺激となります。
- ダニやホコリ、カビ
- ペットの毛やフケ
- 花粉
- 植物や接触性アレルゲン
など
非アトピー型喘息
アレルギーとは関係なく、次のような要因で発症することがあります。特に多いのは、風邪などの感染症をきっかけに咳が長引き、喘息へと進行するケースです。また、肥満との関係も深いことがわかってきており、体重管理も予防の一つとされています。
- 風邪やインフルエンザなどのウイルス感染
- 気温や湿度の変化
- 過労やストレス
- 喫煙、運動、大気汚染
- 肥満
- 食品添加物や一部の薬剤
など
気管支喘息の診断
診断のためには、次のような検査を実施します。
呼吸機能検査
空気の通り道(気道)の状態を調べる検査です。呼吸の勢いや量を測定し、気道が狭くなっていないか確認します。また、気管支拡張薬を吸入した後に呼吸機能が改善するかをみることで、喘息かどうかの判断材料になります。
痰の検査や呼気中一酸化窒素(NO)の測定
気道に炎症があるかどうかを確認します。吐いた息の中の一酸化窒素の濃度が高いと、気道の慢性的な炎症が疑われます。
血液検査
アレルギー体質かどうかを調べ、喘息の原因となる物質(アレルゲン)に対する反応を確認します。
気管支喘息の治療

症状が落ち着いていると、「もう治った」と感じるかもしれませんが、気道では炎症が続いていることが多くあります。この炎症を放っておくと、再び発作が起こりやすくなるだけでなく、学校や仕事、日常生活に支障が出てしまう可能性があります。さらに、炎症が長く続くと気道が段々と固く狭くなり、元の状態に戻りにくくなってしまいます。そうなると、治療しても症状がなかなか改善しづらくなってしまいます。
そのため、喘息の治療では呼吸器内科医による専門的な治療が必須となり、「症状がないときでも、気道の炎症を抑える薬」を継続的に使うことが大切です。中心となるのは吸入ステロイド薬で、気道の炎症を抑えて発作を防ぐ働きがあります。正しく使えば副作用も少なく、安全性の高い治療法です。治療は、喘息の重症度や症状の経過に応じて、薬の量を調整したり、他の薬を追加したりしながら進めていきます。
また、アレルギーが原因の場合は、アレルゲン(ホコリ、ペットの毛など)を避けることも重要です。喫煙されている方は、禁煙も大切な治療の一環です。万が一、発作が起きた場合には、即効性のある気管支拡張薬(発作止め)を使用して症状を和らげます。
重症喘息でお困りの方へ
重症喘息とは?
喘息の薬をしっかり使っても、咳、息苦しさ、喘鳴(ヒューヒュー、ゼーゼーと言う音)が続く場合は、重症喘息の可能性があります。
(※ただし、すべてのケースが重症とは限らず、花粉や喫煙など悪化の原因がある場合や、喘息以外の他の病気が関係している場合、喘息の治療が不十分な場合なども考えられます。)
気になる症状が続く方、今の治療で十分な効果が出ていない方は、一度当院までご相談ください。
重症喘息の治療
これまでの治療で効果が不十分な方には、「生物学的製剤の注射」という新たな選択肢があります。現在、5種類の注射薬が使用されており、患者様の症状に合わせて使い分けます。
使用される主な注射薬
①12歳以上で呼気一酸化窒素(25ppb以上)が高い場合や好酸球数が多い場合
デュピクセント®(デュピルマブ)
➁12歳以上で好酸球が多い場合(150/μl以上)
・ヌーカラ®(メポリズマブ)
➂15歳以上で好酸球が多い場合(150/μl以上)
・ファセンラ®(ペンラリズマブ)
④6歳以上でダニやカビなどにアレルギーがある場合(血清中総IgE濃度が30~1500IU/ml)
・ゾレア®(オマリズマブ)
➄12歳以上で上記の4つの注射でも効果が乏しかった場合
・テゼスパイア®(テゼペルマブ)
生物学的製剤のメリット
- 喘息の発作頻度や入院を減らすことができるため、生活の質(QOL)が向上する
- ステロイドの量を減らすことにより、副作用のリスクを減らすことができる
生物学的製剤のデメリット
治療費が高額になる場合があります。(※自己負担額は年齢や所得によって異なります。)
高額療養費や医療費控除といった制度が使える場合もありますので、ご相談ください。