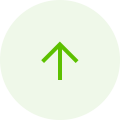アレルギー性鼻炎(花粉症)か
どうか確かめるには?

アレルギー性鼻炎(花粉症)の大きな特徴は、アレルギー物質である花粉が飛んでいる間にだけ症状が現れることです。
スギ花粉を例として、飛散がピークになる2月から4月に次のような症状があれば、「花粉症」が疑われます。
- 連続してくしゃみが出る
- 水のようにさらさらした、透明の鼻水が出る
- 目の痒くなったり充血したりする
- 微熱が出る
- 花粉の飛散時期に2週間以上継続して症状が出る
アレルギー性鼻炎
(花粉症)とは?
アレルギー性鼻炎とは、花粉などのアレルゲンの吸入がアレルギー反応を引き起こし、くしゃみや鼻水、鼻詰まりなどの症状が現れる病気です。鼻の症状以外にも頭痛や微熱、倦怠感や耳や口の痒みといった全身症状が生じることもあります。アレルギー性鼻炎は、主に次の2種類に分かれます。
通年性アレルギー性鼻炎
通年性アレルギー性鼻炎の場合、鼻炎症状は一年を通して現れます。原因にはハウスダストやダニ、カビ、動物の毛などがあります。
季節性アレルギー性鼻炎
季節性アレルギー性鼻炎は「花粉症」とも呼ばれ、特定の季節にのみ症状が現れるのが特徴です。春の季節に飛散するスギやヒノキがよく知られていますが、秋のイネ、ヨモギ、ブタクサなどが原因の花粉症もあります。
アレルギー性鼻炎(花粉症)を和らげる方法は?
ハウスダストやダニ、動物、各種花粉に対するアレルギーがあるかどうかを血液検査で確認することが可能です。
また、症状が悪化するタイミングが把握できれば、アレルギー症状の原因となる物質が何であるかを明らかにするために役立ちます。原因が判明すれば、できるだけその物質と接触しないようにすることで、症状が軽減できる可能性があります。
花粉が原因
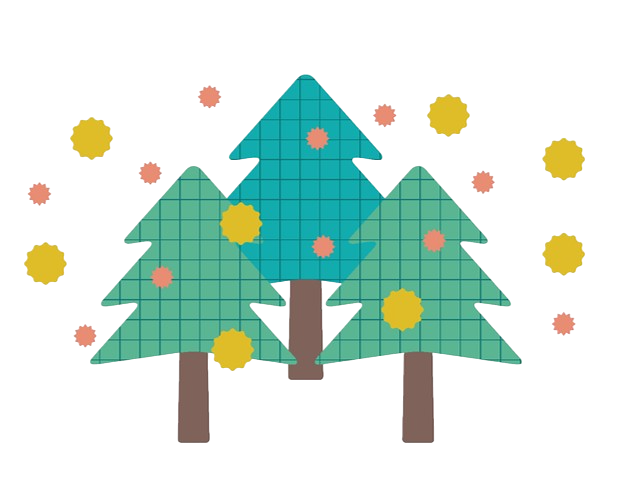
- 外出の機会を減らす
- 外に出る際はマスクやメガネを着ける
- 家に入る前に、衣服や髪をよくはらう
- 帰宅したらすぐに洗顔やうがいをして鼻をかむ
- 換気は最低限にし、できるだけ窓を閉めておく
- 布団や洗濯物を外に干さない
- 部屋の掃除をこまめに行う
ダニが原因
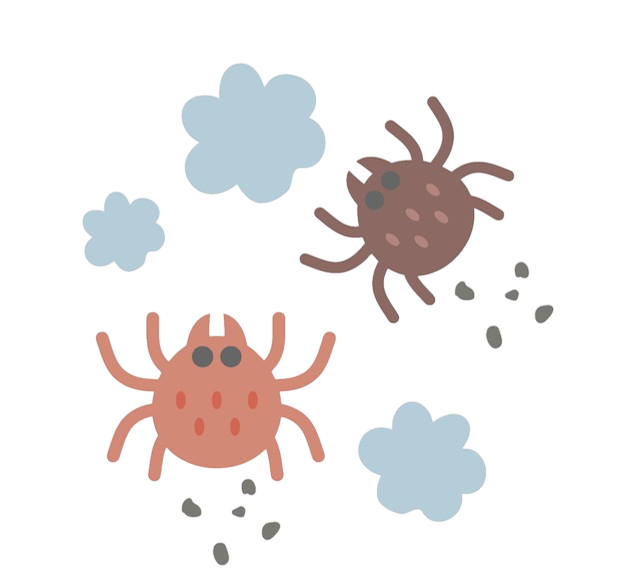
- 週に2回以上掃除機をかける(布団は週に1回以上)
- ファブリック素材(布)のソファーやカーペット、畳をできるだけ使用しない
- ベッドのマットや布団、枕にダニを遮断するカバーを使用する
- 週に2回以上布団を干す、または乾燥機を使って乾燥させる
- 週に1回以上シーツやカバーを洗濯する
ペットが原因

- 可能な限り屋内に入れない、ゲートなどで区分けをする
- 定期的にシャワーで洗う
- カーペットではなくフローリングにする
- 部屋をこまめに掃除する
アレルギー性鼻炎(花粉症)の治し方
飲み薬による治療
アレルギー性鼻炎の治療の中で特によく行われる治療は、「飲み薬」によるものです。アレルゲンが体内に入るとヒスタミンの量が増えるため、抗ヒスタミン薬を使用することでそれを減らし、くしゃみや鼻水といったアレルギー症状を緩和することができます。
抗ヒスタミン薬には多くの種類があり、市販でも購入が可能ですが、病院で処方を受けると公的保険が適用になるため安価になるケースが多いです。眠気や倦怠感などの副作用がみられる方や妊娠中の方には、漢方薬を処方するというケースも増えてきています。
注射による治療
アレルゲン免疫療法
アレルゲン免疫療法は、アレルギーの原因となる物質(アレルゲン)を身体に少しずつ取り入れることで、身体をアレルゲンに慣れさせ、症状を和らげたり、体質の改善を目指す治療法です。「減感作療法」とも呼ばれています。
この治療では、はじめにアレルゲンを「皮下注射」で体内に少量ずつ投与していきます。治療は週に1〜2回の頻度でスタートし、身体が慣れて副作用などが出なければ、2週間に1回程度の通院に切り替わります。
重い副作用はまれですが、アナフィラキシーショックといった強いアレルギー反応が起こる可能性もあるため、特に最初の投与には注意が必要です。効果には個人差がありますが、およそ7割の方に症状の改善がみられ、体質そのものが改善される(根治する)ケースもあります。たとえ根治に至らなくても、症状が軽くなることで日常生活が大きく楽になります。
アレルギー性鼻炎の症状に悩んでいる方や、症状が強いお子様にとっても、前向きに検討できる治療法です。また、皮下注射以外にも、舌の下に薬を入れて吸収させる「舌下免疫療法」という方法もあり、こちらも有効です。
ヒスタグロビン注射
ヒスタグロビン注射は、「ヒト免疫グロブリン」と呼ばれる、人の血液から作られた成分を使った治療薬です。
スギ花粉やダニなど、特定のアレルゲンに対して行うアレルゲン免疫療法とは異なり、ヒスタグロビン注射はアレルゲンの種類を問わず、幅広いアレルギー症状に効果が期待できる「非特異的減感作療法」に分類されます。
この注射は、気管支喘息やアレルギー性鼻炎、花粉症など様々なアレルギーに対応できるのが特長です。
治療は通常、週に1~2回のペースで通院していただき、6回の注射を1クールとします。効果が不十分な場合は、薬の量を調整しながら継続して治療を行います。効果が現れてからは、3~4か月に1回の頻度で注射を続けていきます。
ステロイド注射(保険適用外)
ステロイド薬は炎症を抑える効果のある薬として知られていますが、アレルギー性鼻炎の治療でステロイド注射が使用されることは、現在ではほとんどありません。
ステロイド注射は強い炎症抑制作用を持つため、1回注射を打つとその効果は2~3か月間持続します。しかし、ステロイド薬は全身の細胞への影響があるため、高い副作用のリスクもあります。
特に重症の副作用には感染症の誘発・骨粗しょう症・消化性潰瘍・血栓症などがあり、これらは生活に支障をきたすケースもあります。ただし、注射ではなく点鼻のステロイド薬であれば安全度も高く、ガイドラインでも使用が認められている治療法になります。
ノイロトロピン注射
ノイトロピン注射は、アレルギー性鼻炎以外に、皮膚の痒みや神経痛など、様々な症状に効果がある治療薬です。
アレルギー性鼻炎に対してノイロトロピン注射を使用した臨床試験では、くしゃみや鼻水、鼻づまりの症状が軽減したと報告されています。投与期間は6週間ですが、2週間投与し十分な効果がみられない場合は投与を止めます。他の薬とは効き方が異なるため、内服薬などと併せて使用することもできます。
これまでの治療で満足に効果が感じられなかった方にとっても、症状の改善が期待できる治療法です。
ゾレア皮下注用
ゾレア皮下注射は、これまでの治療では十分な効果が得られなかった重症以上のアレルギー症状をお持ちの方に使用される注射薬です。
ゾレアは「モノクローナル抗体」と呼ばれるタイプの薬で、動物の細胞を使って作られた、人の抗体に似た働きをする成分です。この抗体がアレルギーの原因物質(アレルゲン)が細胞に結びつくのを防ぎ、体内での炎症反応を抑えることで、症状の改善を目指します。
アレルギー性鼻炎(花粉症)の重症度は、鼻づまりやくしゃみ、鼻水の頻度や程度で判断されます。ゾレアが使用される「最重症」の例としては、1日中鼻がつまって息がしづらい、くしゃみや鼻水が1日に21回以上出るといった状態が挙げられます。
治療は、2週間または4週間に1回の頻度で注射を行い、血液検査の結果などに基づいて、その方に合った適切な量を決めていきます。重い症状に悩まされている方にとって、有力な治療の選択肢となります。
舌下免疫療法による治療
舌下免疫療法は、花粉症の根本的な改善(根治)を目指すことができる「減感作療法」の一つです。現在、保険が適用されているのは「スギ」と「ダニ」に対する治療のみですが、スギ花粉症は花粉症患者全体の約7割を占めるため、多くの方が保険で治療を受けることができます。
この治療は、花粉が飛んでいない時期(6月〜11月)にスタートし、2〜3年間、毎日お薬を舌の下に服用し続けることが必要です。
必ずしも花粉症が100%治るわけではありませんが、症状の軽減や体質の改善が期待できます。注射を使わないため、注射が苦手なお子様でも取り組みやすく、通院も1〜2か月に1回で済むなど、継続しやすい点もメリットです。アレルギー性鼻炎(花粉症)に長年悩まされている方にとって、有力な選択肢となる治療法です。